 |
 |
2025年度・夏 | |||
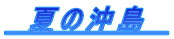
2025年度・夏
今年も沖島に暑い、暑い夏がやってきました。例年なら北風が吹く日もあり暑い中でも少し涼しさを感じられることもあるのですが、今年はそのような日もなく、全国的にも“危険な暑さ”が叫ばれているように、ここ沖島でもあまり経験したことのない“非常に暑い夏”となっています。
この春は“ニゴロブナ漁”の豊漁や冬の大寒波による雪解け水で琵琶湖の水位が改善されるなど明るい兆しを感じ、このまま夏に向けて続いていくことを願っていましたが、今年の梅雨は期待したほどの雨量もなく、その後も雨がほとんど降らず、例年ならこの時期は夕立があるのですが、それもないという状況が続いていることから、琵琶湖も再び渇水状態となっています。この雨が少なく夕立もない状況は琵琶湖だけでなく島内の畑作にも影響を及ぼしています。
このような厳しい夏を迎えている沖島ですが、毎日多くの観光客の方々がお越しになり、島に活気をもたらして下さっています。また、毎年恒例となりました「ふなずし手作り講習会」も今年で17年目を迎え、全日程を滞りなく無事に開催させていただくことができましたこと、感謝とともに安堵いたしております。

そんな夏を過ごしている沖島からこの夏の話題をお届けいたします。
令和7年・夏の話題
今年の夏の漁…なかなか期待通りにはいきません
今年も暑さ厳しい夏を迎える中、漁の様子も“夏の漁”へと移り変わりました。この春は“ニゴロブナ漁”の豊漁や琵琶湖の水位が改善されるなど明るい兆しを感じるスタートとなり、夏に向けて続いていくことを期待していましたが、なかなか期待通りにはいかないようです。
琵琶湖の水位も春には改善してきていたものの、今年の梅雨は期待したほどの雨量もなく、その後も雨が降らないうえ、この猛暑続きで水位がどんどん低下し、現在(8月5日)、−41cmまで下がり再び渇水状態となっています。
春から続けられている“小アユ漁”は5月頃の刺し網漁で少しずつ水揚げが上がるようになりましたが、獲れるポイント(場所)が特定的だったことなどから、このまま夏に向けて水揚げが増えていくかが懸念されていましたが、懸念していた通りの結果となり相変わらず獲れない状況となっています。このことは夏を迎えて南風が強く漁に出られなかったり獲れないことによるモチベーションの低下などから漁を休みがちになっていることや冬の“ヒウオ(小アユの稚魚)漁”が過去にない不漁だったように、もともと稚魚が少なかったことも水揚げが少なくなっている要因と思われますが、この猛暑により琵琶湖の水温が高いことなども漁に何らかの影響を及ぼしているのではないか・・・と懸念しております。
“小アユ”
また、この暑さと琵琶湖や河川の渇水状況は、これから迎えるアユの産卵にも大きな不安材料となっています。天然のアユは9月頃から河川に遡上して産卵する時期となりますが、この渇水状況と水温の高さでは自然産卵は見込みがないのでは・・・と懸念されます。一方、人工河川による産卵は今年も行われますが、水産試験場によると、昨年は9月から稼動させたものの水温が高すぎて全滅だったことから、今年は例年より時期を遅らせて水温が下がるのを見計らって行う予定だそうです。自然産卵の望みが少ないと思われることから人工河川頼みとなりますが、産卵に適切な水温に下がるまでにどのくらいかかるか、その後の生育環境など難しい問題もあり懸念は残ります。
夏に最盛期を迎える“ビワマス漁”は、今年も沖島の水揚げは少なくなっています。昨年も“ビワマス漁”をする漁師が高齢化により5,6隻となってしまったこともあり水揚げが少なかったのですが、今年は更に減り2隻となってしまいました。また、今年は一回の漁で5〜6尾しか獲れず、サイズも小さいようです。原因はわかりませんが、春からビワマス釣りを引き続き行っている人からも「釣れない」ということを聞いており、ビワマスの育ちが悪い状況なのかもしれません。夏に獲れるビワマスは全身に脂がのり、刺身は“琵琶湖のトロ”と称されます。2、3年前までは、2kg以上の大きさのビワマスが何十キロと獲れていましたが、ここ最近はビワマスもあまり獲れなくなってきており“幻の湖魚”と言われるようになるのではと先行きが懸念されます。
ビワマス刺身“琵琶湖のトロ”
ここのところ不漁が続いている“スジエビ漁”は、最近「えびたつべ漁」で少し獲れていますが、水揚げ量としては、まだまだ少なく、漁協婦人部『湖島婦貴の会』の沖島産“えび豆”も引き続き販売中止を余儀なくされています。
その他“ホンモロコ漁”は、この夏も沖島では漁を行っていません。かつては、この時期のホンモロコは脂がのっており、“夏もろこ”と呼ばれ需要も多かったのですが、最近は需要が減ったため漁をしなくなっているのが現状です。
夏に解禁となる“ウロリ漁”は予定通り7月20日に解禁となり漁が始まりました。「ウロリ」とは「ゴリ(ヨシノボリの稚魚)」のことで、そうめんのように細く白い魚で成魚でも1.5cmくらいの湖魚です。解禁前に雨が少なかったため、今年の漁はどうなるか懸念されていましたが、解禁当初はあまり獲れなかったものの8月に入ってからは例年通り獲れるようになり、漁をする船も20隻ほどあることから例年並みの水揚げ量が期待できるのでは・・・と思われます。しかしながら、夕立もないこの夏の気候が、この先の“ウロリ漁”にどう影響してくるかなど心配はつきない状況です。
また、8月末から9月にかけて“ワカサギ漁”も始まります。現時点でも小アユ漁の刺し網についてきており、漁が本格的に始まれば昨年と同様に水揚げ量が期待できるのでは・・・と思われます。しかしながら、原因は不明ですが、ここ最近、ワカサギの産卵時期が早くなって来ており、以前は冬が産卵時期で子持ちのものが獲れていましたが、昨冬は既に産卵を終えているなど湖魚の生態が掴みづらくなってきています。このことは経験値を活かす事が出来ず漁のし辛さにも繋がってしまうことから、この夏の酷暑や渇水がワカサギの生態に影響を及ぼさないことを願うばかりです。
ここまで夏の漁の様子などをご紹介して参りましたが、この夏は渇水状況は厳しいものの特に琵琶湖に目立った環境の変化はないように感じています。しかしながら、ビワマス漁の船が減るなど高齢化による継続の難しさを今年も実感する夏となりました。出来ることなら・・・昔のように何も変わらず魚がもう少し獲れるようになると一番良いのですが、なかなかそうはいかないのが現状です。これからも琵琶湖を取り巻く環境の変化を注視しつつ、伝統や琵琶湖の恩恵を引き継いでいくために前向きに取り組んで参りたいと思います。
“小アユ山椒入り若煮”
“うろり若煮”
“わかさぎ若煮”
★ 沖島漁協婦人部“湖島婦貴の会”では、ご家庭でお気軽に湖魚の佃煮など“沖島家庭の味”を楽しんで いただきたく、『通信販売』も行っております。ぜひ、こちらもご利用くださいませ。
詳しくはこちら・・・通信販売「沖島“家庭の味”宅配便」
今年も大盛況に感謝です♪…『ふなずし手作り講習会』
毎年、ご好評をいただいております琵琶湖汽船・沖島漁協共同企画『ふなずし手作り講習会』を今年も7月3・6・9・12・15・18・21日の日程で開催致しました。今年はどの回も晴天となり猛暑の中での開催となりましたが、開け放した倉庫の中で大型扇風機などを設置し、皆様にも熱中症対策を心がけていただいたことで、どなたも体調を崩されることなく終えることができました。また、今年の講習会も大変多くの皆様にご参加いただきましたことに感謝申し上げるとともに、毎回和気あいあいとして雰囲気の中、トラブルもなく全日程を滞りなく終えることができましたことも参加者皆様のご理解とご協力の賜物と併せて感謝申し上げます。
今年の「塩切り鮒」は、この春の“ニゴロブナ漁”が豊漁だったことから、20cm以上の小さ過ぎず大き過ぎないサイズの卵の抱え方も良いもので揃えることができました。魚のサイズが揃っていることは漬け上がりにムラがなくなり、美味しく漬け上がることに繋がります。今年もより一層美味しい鮒ずしになるのでは…と、今から期待が膨らみます。
今年の講習会も非常に厳しい暑さの中での開催となったことから、大型扇風機やスポットクーラーなどの暑さ対策をさせていただき、「熱中症予防」を心がけていただくよう、声かけをさせていただきながら進行させていただきました。
講習会の内容は、毎回10:20頃より始まり、午前中は塩切り鮒を洗い(磨き)、吊るし干しする作業をしていただきます。乾かしている間、昼食をとっていただき、午後(13:30)から漬け込み作業をしていただきます。15時までには漬け込み作業が完了し講習会終了となります。
「昼食タイム」は漁協会館2階を昼食会場とし、今年も沖島で水揚げされた湖魚、沖島産の野菜を活かした“沖島の味満載のお弁当(有料・要予約)”をご用意させていただきました。どれもご好評をいただき、その中でも“琵琶湖産鯉の煮付け”は大変ご好評をいただきました。また、2階で実演販売させていただいた“アユの塩焼き(有料)”も毎回完売となるご好評をいただきました。
“沖島のやさしいアイス(有料)”
もご好評いただきました♪
その他、よく冷えたビールなども販売させていただき、冷たいビールとともに“沖島の味”を楽しまれる方々もお見えになりました。
昼食タイムの“沖島の味満載のお弁当”
(右の写真はお弁当の内容です)
沖島産の“湖魚の若煮”
“大中産スイカ”
“雄のニゴロブナフライ”
“湖魚の天ぷら”
“沖島産野菜サラダ”
“キュウリの酢の物”
“琵琶湖産鯉の煮付け”
“沖島の鮒ずし”
鮒ずしを漬け込んだ樽は、お持ち帰りしていただくか、または漁協にて保管(有料)させていただきます。保管させていただいた樽は、食べ頃になった頃に樽から鮒ずしを取り出し、一尾ずつ真空パックにしたものをダンボールに入れてご自宅へお送り致しております。鮒ずしは発酵食品ですので、少しずつ発酵が進みますが、真空パックのまま冷凍保存していただければ、食べ頃の状態のまま長期保存ができます。講習会で漬け込みまでしていただけば、樽だしする手間もなく長期保存できるので、より手軽に鮒ずし作りを楽しんでいただけるのではないでしょうか♪ 年々、漁協での保管を希望される方も増えており、今年も半分以上の方々の樽を沖島で保管させていただきます。
この講習会で漬け込んだ「鮒ずし」は、これからの気候にもよりますが、例年11月下旬食べ頃を迎え、毎年「鮒ずし手作り講習会の鮒ずしは食べやすい♪」とのお声を頂戴し、大変ご好評をいただいております。この猛暑で発酵も順調に進むと思われることから、今年も11月下旬頃からずれても12月始めには漬けあがり、樽だしできるのではないかと思います。
この講習会でご紹介している「漬け込み方」は、どなたでも手軽に「鮒ずし作り」を楽しんでいただきたいと“現代のライフスタイルや住環境に考慮した漬け込み方法”として編み出された方法で、漬け込んでから密閉状態のまま保管することにより、水替えの手間や外部への臭いの発生を心配することなく漬け込んでいただくことができます。また、雑菌や虫害などの影響も受けにくくなっております。
毎年開催しております「ふなずし手作り講習会」も今年で17年目を迎えました。今年も大変多くの方にご参加いただきましたこと、大変嬉しく継続していく励みをいただきました。ご参加くださる方々の中にはリピーターの方も多く、「店で買うものより自分で漬けた鮒ずしがいいな♪」と手際よく作業を進められる姿は頼もしく、鮒ずし作りが受け継がれていることを実感するとともに講習会の手応えを感じております。また、年々若い方々の参加も増え、「鮒ずしは食べたことないけど漬けてみたい」という方もみえるなど、いろいろな方に興味をもっていただいていることは大変嬉しく、継続していく上での大きな励みとなっています。また、「塩切り鮒だけ送ってほしい」という方もあり、“塩切り鮒の予約販売”も順調でご家庭で鮒ずしを漬けられる方も多くなってきたのでは…ということも感じております。
しかしながら、その一方では漁協スタッフの高齢化とともに継続していくこと自体が簡単なことではなく、年々大きな課題となってきている現実もあります。2、3年前頃から若いスタッフやサポートしてくださる方々も増え、年々要領も心得えてくださり活躍してくださっていることは、大変心強く感じ受け継がれていく実感を感じさせてくれます。こうして徐々に次世代へバトンを渡していき講習会を継続させていくことも琵琶湖の伝統文化を引き継いでいく担い手としての大きな役割でもあると思います。
今年も講習会を通して多くの方に“私どもが推奨する鮒ずしの漬け込み方”を学んでいただきました。この講習会を通して、この漬け込み方が広まり、再び“鮒ずし”が昔のように各家庭で漬け込まれる身近な食品となれば嬉しい限りです。これからもそんな未来につながるよう、取り組んで参りたいと思います。
※ 講習会で行っている「漬け込み方法」をご紹介しています。
こちらをご覧下さいませ・・・『“おいしいふなずし”漬けてみませんか♪』
この夏の琵琶湖の様子は・・・
この冬の大寒波により雪解け水が多かったことなどにより、この春は琵琶湖の水位も改善してきていたものの、今年の梅雨は期待したほどの雨量もなく、その後も雨が降らないうえ、この猛暑続きで水位がどんどん低下し、この夏の琵琶湖の水位は現在(8月5日)、−41cmまで下がり再び渇水状態となっています。また、猛暑続きで気温が高いことから琵琶湖の水温も例年より高くなっていると思われます。
このような状況ですが、今のところ、漁をしていても大きな異変を感じることはありません。しかしながら、これ以上この状況が続くとこれから先、産卵時期を迎える湖魚などに影響を与えてしまうのでは・・・と懸念され、湖魚の成育にも影響が出てくるのではないかと心配しております。湖魚の生態の変化は漁のし辛さへと繋がっていきます。そのことからも今は只々、雨を待ち望むばかりです。
![]()
![]()
沖島の夏は、初夏の頃から、ビワマス、ウナギ漁が始まり、7月に入ってウロリ漁も最盛期を迎えると、いよいよ夏本番です。 “カラフルな漁網”
漁網の手入れは日々行いますが、漁網の染色は、夏の暑い時期に行います。夏の日差しが染色した漁網をよく乾かしてくれるからです。
最近は、カラフルな色に染め上げるのが流行で、港のあちらこちらに漁網のカラフルな花が咲きます。夏到来を告げる風景のひとつです。
“ふな寿司の漬け込み”
夏の土用の暑い日に鮒寿司の漬け込みをします。春に卵を抱えた“ニゴロブナ”をウロコと内臓を取って塩漬けしておいたものを、いよいよ米飯で漬け込むのです。
夏の土用の頃に行うのは、ふな寿司は最初に発酵を進めることが重要で、この夏の暑さが最適だからです。
こうして、漬け込まれたふな寿司は、11月下旬〜年末年始にかけて食べ頃を迎えます。
今年も“ふな寿司の手作り講習会”を行いました。写真をクリックすると講習会で行っている「漬け込み方法」を御覧いただけます。

《桶に漬け込まれていくふな寿司》
写真をクリックして下さい
![]()
![]()

“ウロリの若煮(佃煮)”&“ウロリの釜揚げ”
夏に漁の最盛期を迎える“ウロリ”は、“ゴリ(ヨシノボリの稚魚)”のことで、この辺りでは“ウロリ”と呼びます。成魚になっても1.5cmくらいのそうめんのように細く白い小魚です。
“ウロリの若煮”は、沖島で水揚げされたウロリを昔から沖島の漁師の家庭に受け継がれている炊き方で炊き上げたものです。佃煮より短時間で炊き上げるので、柔らかく、また水飴等も使わないので、甘辛くてもあっさりとした味に仕上がります。暑くて食が進まない時にも、ご飯が進む一品です。
“ウロリの釜揚げ”は、ウロリが新鮮なうち(水揚げされて1時間以内)に釜揚げにしていただきます。ウロリは鮮度が落ちるのが早く、まさに漁の最盛期を迎える夏にしか味わえない一品です。
※“ウロリの若煮”は漁協婦人部湖島婦貴の会の屋台(漁協会館前)で販売中です
“うなぎの蒲焼き・白焼き”
琵琶湖産天然うなぎは、特大サイズのものが多く、肉厚で脂がとても良くのっています。夏のこの時期は、蒲焼き・白焼きが絶品です。
特に白焼きは、うなぎ本来の味を楽しむことができます。また、ポン酢・生姜醤油で味わうのも、さっぱりしていて暑い夏にピッタリの一品です。
《うなぎを炭火で焼いています》
《ビワマスの刺身の調理例》
“ビワマスの刺身”
琵琶湖では、夏の始め頃から“ビワマス漁”が盛んになります。特に夏に獲れるビワマスは全身に脂がのり、刺身は“琵琶湖のトロ”と言われるほどの味わいです。
“うなぎのじゅんじゅん”
“じゅんじゅん”とは、この地方で言う“すき焼き”のことです。作り方は一般のすき焼きと同じですが、肉類等のかわりに“うなぎ”を入れます。食べ方も一般的なすき焼きと同様、溶き卵にからめたりして頂きます。
また家庭では、写真のようにいろいろな具材を入れるのではなく、玉ねぎとうなぎだけですき焼き風にしたりもします。
《うなぎのじゅんじゅんの調理例》
《参考文献》
「琵琶湖の幸 読本」 平成19年9月発行 滋賀県漁業協同組合